

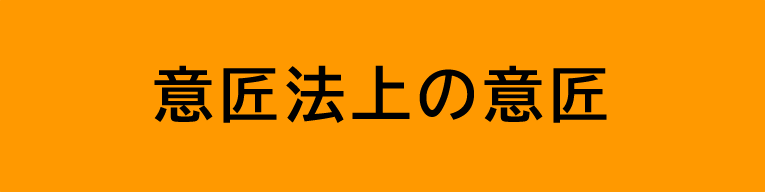 |
1. 意匠法上の「意匠」
意匠法上の意匠とは、「物品(物品の部分を含む。…)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。…)であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの」をいいます(意匠法2条1項)。
「物品」の意匠は、従来より意匠法による保護の対象でしたが、令和2(2020)年4月1日から「建築物」の意匠、「画像」(物品の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの)の意匠が追加されています。
また、「組物」が「同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるもの」となったほか(意匠法8条)、新たに「内装」(店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾)の意匠が追加されています(意匠法8条の2)。
2. 物品の意匠
従来より、意匠は「物品の形状等」であり、物品を離れての意匠はあり得ないことから、意匠は物品と不可分一体の関係にあるものと解されており、意匠法上、「意匠」というためには、単なる形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合というだけでは不十分で、それらが物品に表されたものであることが必要です。意匠がいかなる加工方法によって形成されたものかは、意匠の該当性とは関係ありません。
ここで、「物品の形状」は意匠の構成要素です。しかし、気体、液体、粉状物、光、熱といった一定の形状を有しないものは、そもそも物品の概念になじまないものであり、意匠を構成しません。
「物品の模様」も意匠の構成要素の一つです。意匠は物品と不可分一体の関係にあるため、模様のみでは意匠を構成しませんが、物品の形状と結合したものであれば、意匠を構成します。しかし、物品に表された文字は、それが文字として読み取ることが十分可能であり、いまだ文字が模様に変化して文字本来の機能を失っているとはいえない場合には、模様とは認められず、意匠を構成しません(昭55(行ツ)75)。
「物品の色彩」も意匠の構成要素の一つです。色彩も、それのみでは意匠を構成しませんが、物品の形状等と結合することで、意匠を構成します。
それから、意匠は物品の単なる形状等であるだけではなく、「視覚を通じて美観を起こさせるもの」であることも要件とされています。「美観」とは、物品が本来的に有する機能に基づく美観ではなく、審美的な美観のことをいうと解されます。また、「視覚を通じて」と規定されていることから、物品の形状等が美感を起こさせるとしても、視覚ではなく、触覚、聴覚等を通じて美感を起こさせるものであるときは、意匠を構成しません。
「視覚」が肉眼により認識することに限られるのかは、意匠法の文言からは必ずしも明らかではありませんが、意匠に係る物品の取引に際して、当該物品の形状等を肉眼によって観察することが通常である場合には、肉眼によって認識することのできない形状等は、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たらず、意匠を構成しないと解されます。
他方で、意匠に係る物品の取引に際して、現物又はサンプル品を拡大鏡等により観察したり、拡大写真や拡大図をカタログ、仕様書等に掲載するなどの方法によって、当該物品の形状等を拡大して観察することが通常である場合には、当該物品の形状等は、肉眼によって認識することができないとしても、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たり、意匠を構成すると解されます(平17(行ケ)10679)。
なお、意匠に係る物品については、意匠法施行規則第8条別表第1に掲げられていた物品の区分は令和2(2020)年4月1日をもって廃止され、意匠に係る物品等の例が公表されています。詳しくは、意匠に係る物品等の例をご覧ください。
3. 建築物の意匠
不動産としての建物、住宅、店舗等の建築物は、有体物である動産をいう物品の概念に含まれないことから、動産としての組立て家屋やその部分を意匠法による保護の対象としていましたが、令和2(2020)年4月1日より、不動産である建築物やその部分の形状等も保護の対象に追加されました。
4. 画像の意匠
従来、画像(画面デザイン)の意匠については、物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像であって、当該物品の表示部又はこれと一体として用いられる物品の表示部に表示されるもののみが意匠法による保護の対象とされていましたが、令和2(2020)年4月1日より、保護の対象とすべき画像の概念が拡張され、機器の操作の用に供される画像(操作画像)や機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)が保護の対象となりました。
5. 組物の意匠
組物の意匠とは、同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であって、経済産業省令で定める組物を構成する意匠であり、組物全体として統一があることを要件として、一の意匠として意匠登録出願することができます(意匠法8条)。
組物の意匠といっても物品等から離れての意匠はあり得ないところであり、「組物全体として統一がある」ことを要件としていることからも、組物を構成する二以上の物品等又はその部分の間で統一のある美観を起こさせるものでなければなりません。組物の意匠は二以上の物品等で構成されるものですが、個々の構成物品等を保護するものではなく、あくまで組物全体又はその部分の統一ある美的外観を一意匠として保護するものです。
なお、組物は、現在、意匠法施行規則第8条別表に掲げる43品目となっています。詳しくは、組物及びその構成物品等の例をご覧ください。
6. 内装の意匠
内装の意匠とは、店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠であり、内装全体として統一的な美観があることを要件として、一の意匠として意匠登録出願することができます(意匠法8条の2)。
内装の意匠は、令和2(2020)年4月1日より意匠法による保護の対象に追加されたもので、組物のように同時に使用される二以上の物品等又はその部分の統一のある美的外観を保護するのとは異なり、不動産の一部ともいうべき内装空間を構成している物品等又はその部分の統一的な美観を一意匠として保護するものです。
なお、内装の意匠に係る物品等については、意匠に係る物品等の例に公表されています。詳しくは、意匠に係る物品等の例をご覧ください。
7. 部分意匠
意匠法では、物品の形状等、建築物の形状等又は画像の創作部分を的確に保護するため、物品の部分、建築物の部分又は画像の部分に係る意匠(部分意匠)についても意匠登録出願することができることとしています(意匠法2条括弧書)。
部分意匠といっても、通常の意匠(全体意匠)と同様に、意匠に係る物品、意匠に係る建築物又は画像の用途、内装又は組物(以下、「物品等」という。)と不可分一体の関係があります。したがって、物品等を離れた単なる模様、色彩等のみでは部分意匠を構成しません。
部分意匠を把握するためには、部分意匠に係る物品等、そしてその形状等を把握することは勿論のことですが、それに加えて、部分意匠に係る形状等がその物品等の全体の中に占める位置、大きさ、範囲についても把握する必要があります。
8. 関連意匠
関連意匠とは、自己の出願意匠又は登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠のことであり、デザインコンセプトを共通にする類似意匠群を的確に保護するため、一定の要件の下、自己の先願意匠にかかわらず(意匠法9条1項、2項)、意匠登録を受けることができます(意匠法10条1項)。
関連意匠も、通常の意匠(全体意匠)と同様に、具体的な物品等又はその部分の形状等でなければならず、物品等を離れての「デザインコンセプト」なる抽象的、観念的なものではありません。
また、関連意匠の要件の一つである「本意匠に類似する意匠」か否かも、関連意匠の具体的な構成態様に基づいて判断されます(平17(行ケ)10227)。
9. 技術的思想の創作と意匠
意匠とは、上述のように、物品の形状等、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいい(意匠法2条1項)、専ら物品等の美的外観に関するものであり、特許法上の発明や実用新案法上の考案のような自然法則を利用した技術的思想の創作(特許法2条1項、実用新案法1条、2条1項)とは趣旨が異なります。
したがって、物品等の形状等が、意匠的まとまりを形成して美観を起こさせるようなものの場合は、それが技術的思想の創作に関するものとしても、意匠法による保護の対象となり得ます。
しかし、物品等の形状等が専ら技術的思想に由来するものであって、美感とは無関係な場合は、特許法又は実用新案法による保護の対象になり得るとしても、意匠法による保護の対象にはなりません。
10. 商標と意匠
商標法上、商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として商品を生産し、証明し、若しくは譲渡する者がその商品について使用をするもの(商品商標)、又は業として役務を提供し、若しくは証明する者がその役務について使用するもの(役務商標)をいいます(商標法2条1項)。
しかし、物品等に表された文字商標、図形商標等が意匠と認められるか否かは意匠法上必ずしも明らかではないため、問題となることがあります。
この問題については、意匠法が、意匠の創作、すなわち量産して工業上利用することができる物品等の形状、模様等の美的創作を保護する趣旨のものであることから(意匠法1条等)、物品等に表された文字、図形等が模様化され、その本来有すべき情報伝達手段としての機能を失っていると見られる場合には、模様としての創作性が認められ、意匠を構成し得るといえます。
しかし、物品等に表された文字、図形等が、看者に対してそのように認識させるものであり、かつ認識することが十分可能と見られる場合には、いまだ模様化して文字、図形等の本来の情報伝達手段としての機能を失っているとはいえないため、模様とは認められず、意匠を構成しないと解されます。
11. 美術著作物と意匠
著作権法は、文化の発展に寄与することを目的としたものであり(著作権法1条)、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定した上で(同法2条1項1号)、「美術の著作物には、美術工芸品を含むものとする。」(同条2項)と規定しています。
しかし、著作権法では、応用美術のうち美術工芸品以外のものについては、著作権法による保護の対象となるか否かについては何ら規定されていません。そのため、美的創作物が著作権法上の美術著作物に当たるのか、それとも意匠法上の意匠に当たるのかといった法域が問題となることがあります。
この問題については、(i) 専ら美的鑑賞の対象となりうる創作性を備えた純粋美術や、(ii) いわゆる応用美術、すなわち実用品に純粋美術の技法感覚などを応用した美術のうち、それ自体が実用品であって極小量製作される美術工芸品については、著作権法が保護を予定している対象であり、他方、(iii) 応用美術のうち、実用に供される機能的な工業製品ないしデザインについては、その実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えていない限り、本来、工業上利用することができる意匠、すなわち工業的生産手段を用いて技術的に量産される意匠として保護すべきであり、著作権法が保護を予定している対象ではないと解されます。
12. 意匠の保護
意匠法は、工業上利用することができる意匠について、一定の要件の下で、独占的排他権である意匠権を付与することにより、意匠を保護することを趣旨とするものであり、意匠権の効力は、権限なき第三者が業として登録意匠に係る物品等と同一又は類似の物品等について登録意匠及びこれに類似する意匠を実施する行為に及びます(意匠法23条)。
意匠権の存続期間は、令和2(2020)年4月1日より、意匠登録出願の日(関連意匠の意匠権にあっては、その基礎意匠の意匠登録出願の日)から25年となっています(意匠法21条1項、2項)。※なお、令和元年法改正前の平成19(2007)年4月1日から令和2(2020)年3月31日までに出願されたものについては、意匠権の設定登録の日から20年です。
他方で、商品の形態については、不正競争防止法による保護を受けることもできます(不競防法2条1項3号)。同号は、他人の商品の形態をそのまま模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争行為と規定しており、商品を開発し、市場に置いた者の先行利益を保護することを趣旨とするものです。ただし、同号には適用除外規定があり、日本国内で最初に販売された日から3年を経過した後に商品形態を模倣した商品を譲渡等する行為(同19条1項6号イ)や、商品形態を模倣した商品を善意無重過失で譲り受けた者がその商品を譲渡等する行為(同号ロ)には、保護が及びません。
近年、魅力あるデザインの商品は、ロングセラーとなったり、復刻版がブームとなることもあることから、そのような商品価値を、意匠として長期間にわたって適切に保護することが重要であるといえます。
弁理士へのお問合せ
何かご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所の弁理士へお問合せください。
※こちらの電子フォーム(Word、PDF)をダウンロードしてご利用ください。
042–728–6618 ※24時間(平日)
※こちらの電子フォーム(Word、PDF)をダウンロードしてご利用ください。
042–728–6618 ※10:00〜17:00(平日)